3歳からピアノを始めたわが子たち。
「練習して!」と怒らずに、
どうしたら楽しく続けられるか?
私の40年のピアノ歴と、
2人の息子の実体験から見えてきた
“家庭でピアノをやめさせない育て方”を
シェアします。
- 練習を嫌がる子どもへの対応
- 楽譜が読めないときのサポート
- 毎日の自然な練習の習慣づけ
- ピアノを「好き」でいさせるための家庭の工夫
ピアノは、自己表現のツールです。
あなたのお子さんにも、
ずっと楽しんでほしいから──
今日の記事が、
少しでもお役に立てば嬉しいです。

ピアノは、「辞める時も健やかなるときも」
常に自分を助けてくれるもの。
そして、今は子供たちの
自己表現を大切にしたい。
子供たちの
「ピアノが好き」
を育てたいと考えています。
✅ピアノ、習わせてるけどこどもが練習を嫌がる
✅「楽譜が読めない」「親が教えるのが難しい」と悩んでいる
✅教室で通っているけど、家庭で何を
サポートしたらいいかわからない
という方に届いたらいいなと
思って、記事を書いてみました。
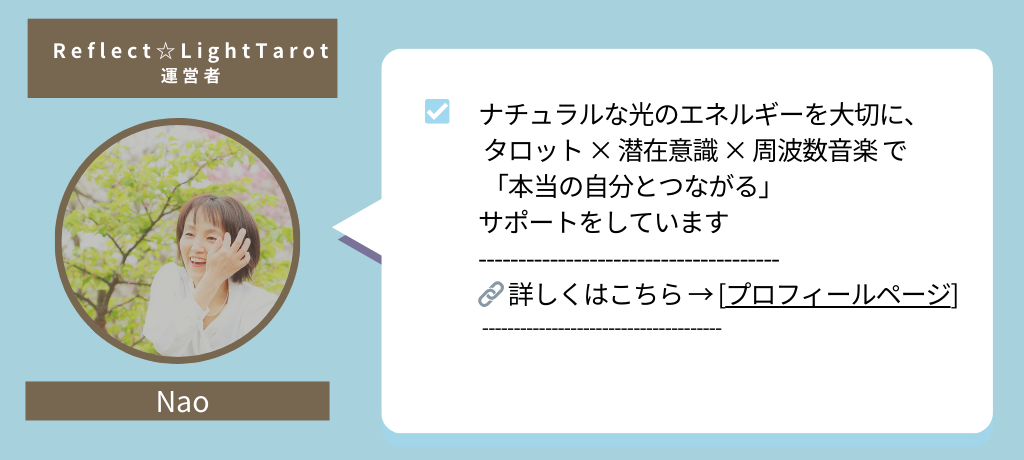
私自身、4歳の時に
ピアノと出会いました。
幼稚園の友達が
上手にピアノを弾く姿を
見て、「私もやりたい」
とキラキラしたのでした。
思えばピアノ歴40年です。
お母さんになっても、
ピアノが大好きです。
ピアノが「楽しくなくなる」理由とは?
こどもがピアノを
始めるとき、
体験教室に参加して
楽しそう。
歌が好きそう。
そう思って入会を
決めます。
でも、実際にレッスンが
始まると、「ワーク」や
「練習」が始まります。
そのあたりから、道が
別れるように思います。
練習しなさいが逆効果になる理由
息子たちは、大手の音楽教室に
通っています。
子供は、「音を自由に鳴らしたり、
自由に表現すること」
が楽しいのに・・・
実際には、まずルールを身に着けます。
✅先生がお話している時は、音を鳴らさない。
✅先生がお話している時は、おしゃべりしない。
✅ピアノの前に来るときは、壁やピアノにもたれない。
等。
そして、毎回「練習してきてね」
と言われます。
親子で参加していますが、
親は「ああ、練習させなきゃな」
と思ってレッスンノートに書き込みます。
そころが、天真爛漫な子どもたちの
中には、「練習しなきゃな」
とは思わないので、
そこで、
練習させなきゃという意識を持つ親と、
そんなこと毛頭頭にない子どもの
間に認識の不一致が起こります。
そこで、親が「練習しなさい」
といった瞬間に、
せっかく芽吹いた楽しいという
気持ちが、シュルシュルと
萎んでいってしまうのです。
ここは、ちょっとしたコツで
親側が工夫できることが
たくさんあるように思います。
よくある親の関わり方とその落とし穴
我が家はグループレッスンにしています。
私は、度重なる引っ越しが
原因で小学校3年ぐらいからは
個人レッスンしかない地方で
ピアノを学びました。
でも、その前までの
アンサンブルの楽しさを
忘れることができません。
特に男の子ということも
あり、
「楽しい」という気持ちを
お友達と分かち合ってほしい
と思って、
グループレッスンにしています。
親子レッスンだと、ついやりがちな
親の関わり方で
先生に注意を受けるケースが
あります。
うまく弾けないこどもに
大人が鍵盤の上から
指で教えてしまうのです。
先生からは
結構厳しく
「教えないでください」
と注意されていました。
間違えてもOK。
大人が助けてしまうと
いつまでも自分で弾けない子に
育つ
という先生からの
愛の鞭メッセージです。
みんなで弾いている時に
自分の子どもが
ドコドコ?とやっている時、
親がガイドして横から助けてあげると
その場では、
助けてあげることができても、
「お母さんがいないと弾けない子」
に育ってしまうので注意が必要です。

ピアノの“楽譜の壁”をどう乗り越える?譜読みの力の育て方
大人が楽譜読めない
だけど、子供にはピアノ弾けるようにさせたいと
考える方も多いです。
誰もが、ドレミのドから
スタートするから、一緒に楽しめばいいのです。

子どもが自分で楽譜を読む力を育てるには?
ピアノが難しくなってしまう一つに
「譜読み」の壁があると申し上げました。
ピアノを習い始めると、
最初に仲良くなるのが
ドレミのドです。
このドのお隣、そのお隣と
一つずつ仲良くなっていくと
いいと思います。
幼児時期の5本の小さな指は、
鍵盤におくと5音に
対応します。
一気にドレミファソです♪
楽しく、楽しく
音の仲間を増やしていくイメージで
抵抗なく楽譜と向き合うように
なれたらいいなと思います。
なぜ「指さしで教える」のは逆効果なのか
ずばり、
いつまでも主体的にできなくなる
からです。
ド
5線の一番下に乗っているのがミ
下から2番目の線に乗っているのがソ
こどもの脳に定着させるためには
繰り返し、見て
自分で覚えるという作業が
必要なのですが、
2人の息子たちは
意外と私に甘えてしまって、
毎回「これは?」
「これは?」
と後ろを振り返って
聞いてくる様子が見られました。
かわいいんですけどね。
いつまでも自分で見つけようと思えなくなるんです。
こどもの、ピアノの先生が
指さしでガイドする親に
本気で注意した光景がわすれません。
私も、ピアノの先生の方針には
同意で、
最終的には「自力で譜読みができる」
ことをさせたかったので早い段階で
突き放しました。
突き放すというと冷たい言い方
ですが、
「あなたが今質問しているミ」は、
すでに
「前にワークで取り組んだミ」
であると
一致させるためのことを
したまでです。
すぐに教えてしまうのは大人も楽ですが。
わざわざ
ワークを出して広げてみせて、
「一緒にやったよね?」
「これと、今あなたが聞いているミは一緒だよ」
と自力で答えさせることを
イチイチするのです。
読み方を覚えた子のやる気は伸びる!
長男も、もっと消極的だったというか
教えないとぐずぐず拗ねたり
していて、習って数年たっているのに
ミとソの区別がつかないということも
ありました。
だから、新しい曲が
宿題になるたびに、
「読めない」
「弾けない」
と泣き出したり、
「できない」と
あきらめてしまった時に、
私の中でプツンと
何かがはじけて、
今のように、
「自力で譜読みができる」
状態にしないとと
使命を感じたのでした。
優しく、ただ寄り添っていただけでは
だめだったと思います。
突然の母の厳しい態度に
当時5歳の息子はやや驚いたと
思いますが、
一番初めに習った時の
昔のワークを横に置いて、
これはド
これはミ
これはソ
と、こどもに納得をさせながら
5線をたどりました。
内心、超めんどくさかったです。
そのおかげで、
小学校3,4年生ごろになると
すっかり譜読みは自立。
新しい曲が宿題で出されても
泣き言を言わず、
一人果敢に譜面を読み進めて
いろいろな曲を楽しんでいます。
その時すかさず「譜読みを一人でできること」について認める、褒めるをしています。
毎日5分でもOK!家庭で自然に習慣化させるコツ
個人レッスンだろうと、
グループレッスンだろうと
毎日の練習は欠かせません。
うちの子ども達には、
自動「毎日5分レッスン」を
幼少期から刷り込みのように
生活に組み込んできました。
それほど、ピアノを長年弾いてきて
毎日の練習が欠かせないことは
体感しているのです。
それでも、「練習がきらい」というお子さんは多いと聞きます。
勉強は習慣化されない長男ですら
気づくとピアノの横に立っています。
シメシメと母はにんまりしております。
この状態になったら、
こどものピアノライフ、
「将来安泰だ」
とも思うのです。
この1日5分ピアノのシステムをこれから説明
します。
ピアノを一番近い位置に配置する
特に、幼児期から
ピアノの練習を習慣化させるために、
ピアノをリビング奥に置くようにしました。
アクセサビリティ=アクセスのし易さ
です。
我が家は、テレビを置く位置に
どーんとピアノを持ってきました。
ドアを開けると、奥に
ピアノが視界に入るのです。
正確にいえば、「視界に入るように設置した」のです。
このおかげで、
長男、次男ともに
自然とピアノのおいてある場所に
向かうのです。
ピアノの場所に向かうと、
自然と蓋を開ける。
蓋を開けたら、弾きたくなる。
のでしょう。
宿題とかこなしていたら、
あっという間に5分なんて
続けられるのです。
極意「質」より、「毎日弾くこと」を優先した
私自身は、桐朋音大1期卒のそれはそれは厳しい
先生の元でレッスンを受けており、
質がかなり大事で、
厳しいレッスンです。
練習も1時間ではとうてい足りません。
指のトレーニングで1時間、プラス
曲作りで時間をかけています。
それを息子たちには
強要はできません。
楽しく、とにかく
自己表現で音楽を奏でてほしいだけ。
だから、しっかり分けます。
ただ、理想の表現をするために
ある程度の技術は必要になってくるでしょう。
だから毎日5分の継続です。
極めたければ、それはその時がきたら。
今は、レッスンに参加するための
宿題の曲、演奏スキルを向上するための
日々の練習重視です。
自然とピアノに向かう声掛け
ご飯ができるちょっとの間。
お風呂が沸くまでのちょっと待っている間。
こういう時間に、
さっと5分なら子ども達も
嫌がりません。
まだ習慣化途中の
次男の方は「えー」とか
「練習は嫌だ」
などはっきり文句を言うときも
ありますが、
長男へのライバル意識から、
背中をみて
「毎日やるものだ」と
刷り込まれています。(母ニンマリ)
次男は、幼稚園の登校前に、
着替えが終わって、
私が送迎の準備をしている
時にグループレッスンの宿題
を練習してもらったり、
一緒に歌を歌ったりして
リマインドしています。
習い始めたら
その日のうちから、
レッスンに向けて、
毎日練習する。
毎日練習して、レッスンに参加する。
このルーティンを
習慣化させるようにしています。
先生には事前アンケート用紙に、「ほめて欲しい」とお伝えしてありました。
毎日頑張って、練習していき、
レッスンでは先生という親ではない
第3者の立場から、
ほめてもらえる。
ほめてもらいたいから、頑張れる!!
親も一緒にピアノと向き合うことで、自然に練習が習慣になる
朝は、次男。
夕方は、長男。
そして、皆が寝静まった深夜に
ヘッドホンを付けてガンガン弾く私。
私からしたら、厳しい先生のレッスンで
必死に練習するわけですが、
それが、いつしか子供たちのなかに
「ピアノって練習するんだ!」
という意識が芽生えたように思うと、
家族が話していました。
なるほどそんな一面もあるかなと思いました。
ただ、そんなピアノ弾きのいる
家庭でなかったとしても、
希望があってピアノを始めたのに、
途中でやめてしまう人をたくさん
見てきました。
親が、
自分がピアノ弾きじゃなくても
「毎日5分の練習」と
「自力の譜読み力」で
楽しい音楽の世界が開かれていくという
ことを伝えていきたい
と思っています。
ピアノは“自己表現のツール”|途中でやめない力を育てたい
発表会に参加すると、
小学生や中学生の人数が
が減ったなーと感じることがあります。
習い事や受験のため
塾で忙しくなった等。
両立が大変だと思われるかも
もしれない。
でも、たった5分、10分。
気分転換にでも
ぜひ音楽による
自己表現をお子さんが
続けてほしいと願っています。
「ピアノのある暮らし」で育つ愛と感性
グループレッスンを長く
続けていると、
アンサンブルの楽しさを味わうことが
できます。
自分のパートを責任もって
て仕上げ、
仲間の音と合わせるのです。
毎年1回の発表会は
毎回楽しませてもらっています。
「ピアノのある暮らし」
とは、毎年時期がくると
発表会の曲が決まり、
そこから本番まで
集中レッスンが始まるのです。
本番では、皆それぞれが
音楽に入り込み、
息を合わせて演奏をそろえる
様子に、それぞれの
曲への向き合い方の集大成を
本番で見せてもらえるし、
普段はパート練習ですが、
会場で全員の音が
そろうのでなおさら感動するのです。
今年は、さらに楽しいことが
ありました。
音楽教室主催の
イベントに誘われて、
憧れのミセスを
パフォーマンス隊、
演奏隊の
一員となって演奏しました。
年齢を超えて、
多忙さを乗り越えて、
こういう表現の場は
素晴らしいなと思います。
演奏・パフォーマンスの
当事者はもちろん、
鑑賞する側と
感動を分かち合うことが
できるのです。
楽譜が読めることで、
どんな新しい曲にも
参戦していける力が
つくのです。
一般的には
偏差値高い学校に入って、頭いい。
テストで100点とかが
優秀だとか
言われたりしますが、
「楽譜を読めること。」
「ピアノを弾けること。」
この力も、こどもの
自己肯定感を高めると
考えています。
まとめ
練習しないこどもにイライラして、やめさせた。
やる気がないこどもに「もったいないからやめる」
「忙しいからピアノどころじゃない」
「ピアノはここまで」
といった声を聞くと、
少し残念な気持ちが
あります。
周囲でも、多くの仲間たちが
グループレッスンから
離れていきました。
私はピアノを長年楽しんでいますが、
せっかく始めたのに、
うまく続けられないという
悩みを聞くことがあります。
親ができることは何でしょうか?
ずばり
親は教えない
です。
親は弾けるけど、
親は教えない方がいいと
思っていて、
私自身こどもたちは
グループレッスンに
通わせています。

お友達と合わせる喜びを
味わってほしいのです。
親ができる「見守る応援」とは
✅親は、教えてはいけない
✅親はガイドしてはいけない
✅親はこどもに強いてはいけない
大切に大切に、
ピアノを弾くこどもを
育てるために親ができること。
①環境づくり
ピアノへのアクセサビリティ(アクセスの良さ)
を整えること。
上に、何もない状況
足元に、物がない状況などなど。
※我が家では、
床に8両、9両、10両に連結された
プラレールが散見されますが、
ピアノの周辺だけは、何もない状態を死守
しています!
そして、日々の
隙間時間にたった5分でいいので、
ピアノの前に座ってもらう。
練習の習慣作り
これだけじゃないでしょうか。
幼児期は親子レッスン、
その後は、こどもだけがレッスン室に
入る時期がきます。
感情の解放。
つらいこと、悲しいこと、
楽しいこと、愛する気持ち
そういう気持ちを
有名な音楽家達は
ピアノで奏でてきました。
情感豊かな子ども達が
ピアノをやめないで、楽しく
続けて欲しいなと
願っています。

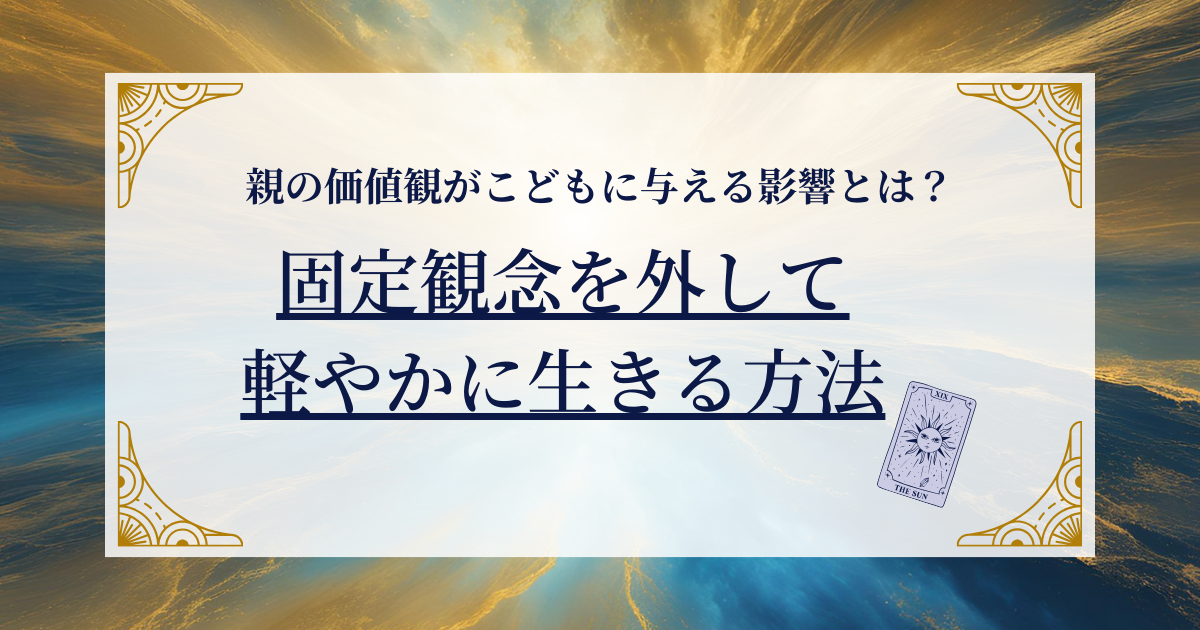
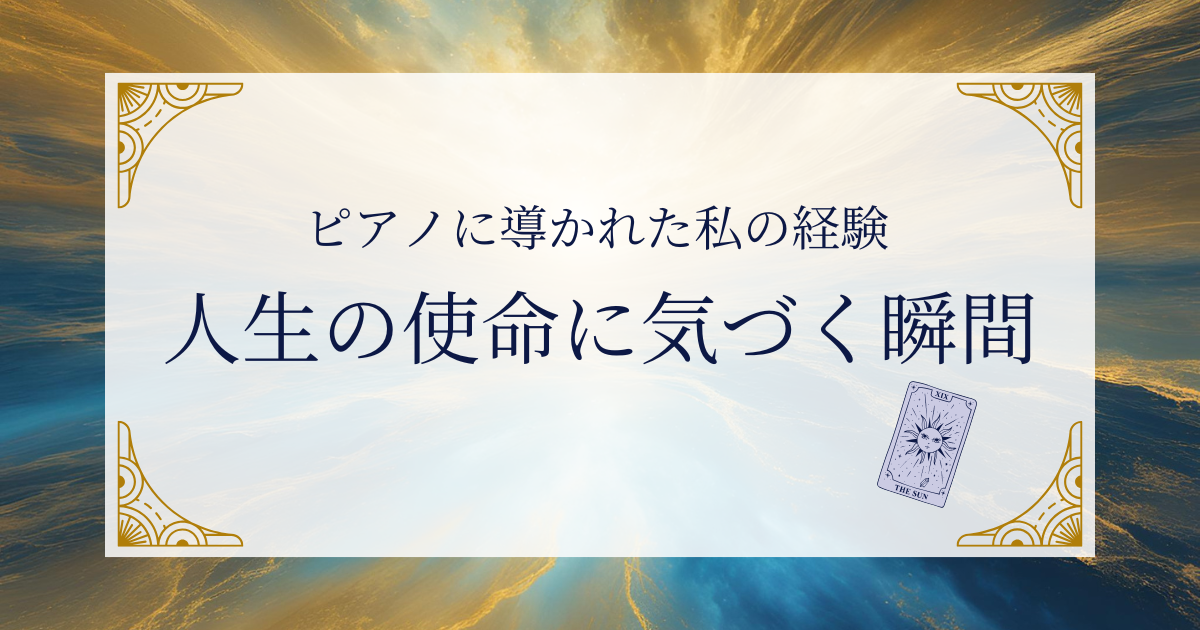
コメント